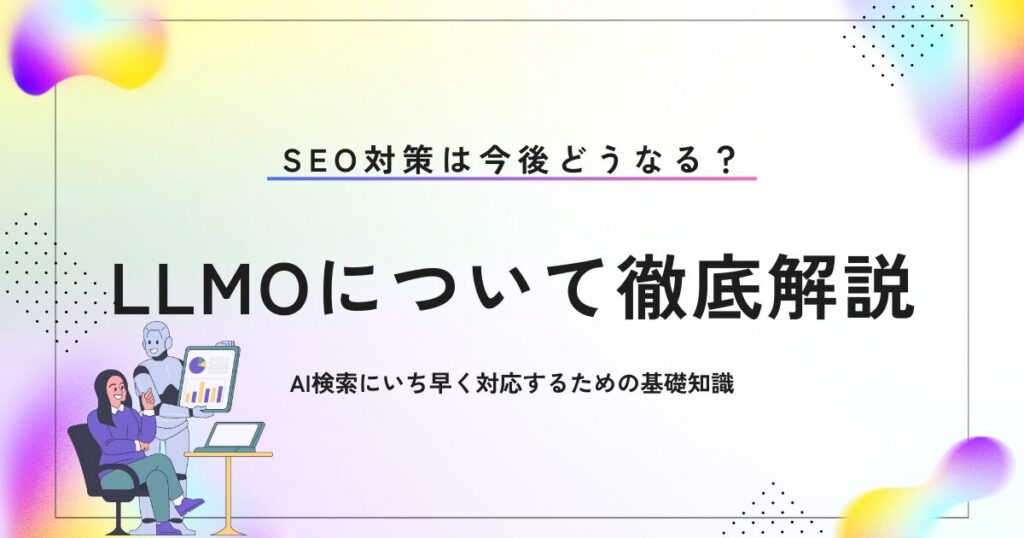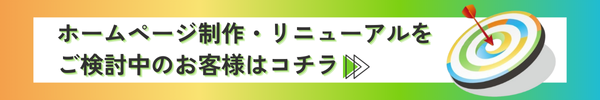目次
はじめに:AI時代におけるSEOとLLMO(大規模言語モデル最適化)の新潮流
検索エンジンの世界は、従来の「キーワード」や「検索順位」だけを追う時代から、より広範で複雑な構造を持つ最適化へと進化を遂げつつあります。
特に生成AIの進化によって、従来のSERPs(検索結果ページ)を通じたトラフィック獲得とは別に、AIそのものに取り上げられるかどうかという視点が、SEO戦略において無視できない要素となりました。
これを最適化する概念が、いま注目を集めている”LLMO(Large Language Model Optimization)”です。
近年、Googleが提供する「AI Overview」機能や、ChatGPT、Geminiなどの生成AIプラットフォームにおいて、ユーザーの検索行動が“AIの出す答えを見る”という方向にシフトし始めています。
そのため、もはや単なるキーワード順位だけでは、正確な検索流入やCV(コンバージョン)への影響を測れなくなってきています。
こうした時代背景のもと、Ahrefsが新たに開発した「Brand Radar」は、まさにLLMO時代の可視化ツールとして期待されています。
本記事では、AhrefsのBrand Radar機能を中心に、どのようにして自社がAIによって言及される機会を増やし、AI時代においても継続的な集客チャネルを確保していくか、その実践的なノウハウと戦略を紹介していきます。
1. Brand Radarとは何か?AI検索結果における言及状況を可視化する最新ツール
Brand Radarは、GoogleのAI Overviewなど、AIベースで生成される検索結果の中で、自社ブランド名やURLがどの程度言及されているかを測定・可視化できる点が最大の特徴です。
例えば、従来のSEOでは、Googleの10位以内にランクインするかどうかが主な成功指標でした。
しかし、AI Overviewが出現することで、ユーザーはAIが自動生成した回答だけを読んで満足してしまい、そもそも通常の検索順位を見ないケースが急増しています。
そのため、AIの生成結果そのものに取り上げられることが、集客の新たな入り口となりつつあるのです。
Brand Radarは、こうしたAIによる「ブランド言及」や「AI露出量」の可視化を可能にするツールで、以下のような機能を提供しています。
主な機能と特徴
- AIチャネルにおけるブランド言及回数の集計:Google AI Overviewにおけるブランド名の登場回数を自動取得
- 言及されたクエリの特定:どの検索クエリでブランドが取り上げられたかを個別に確認
- 競合ブランドとの比較分析:複数のブランドを同時に登録し、AIにおける露出量を時系列で比較
- クリック予測値の可視化:該当クエリの月間検索数と掛け合わせて、想定インプレッションの推定
このように、AI時代のSEOでは、「AIが注目するコンテンツとは何か」「自社はどう評価されているか」といった、これまで曖昧だった指標が数値として明確化されるようになってきたのです。
2. Brand Radarの導入手順と活用の流れ
Brand Radarは以下のようなステップで導入・活用が可能です。
2.1 トピックとブランドの登録
まずは、調査対象となる「領域トピック」(例:クレジットカード、電気自動車、SaaSなど)を設定し、そのトピックに関連する自社ブランドおよび競合ブランドを登録します。
このとき、地域を「日本」に指定することで、日本語のAI Overviewに絞って分析が可能です。
対象ブランドは複数登録できるため、自社だけでなく競合の言及状況も横断的に見ることができます。
2.2 言及傾向の可視化
登録が完了すると、週次や月次でブランド言及数の推移グラフが表示されます。
これにより、自社の露出が増えているか、減っているか、特定の時期にイベントやメディア露出などが影響しているかなどが一目瞭然となります。
2.3 ギャップクエリの発見
Brand Radarで最も実用的なのが「未言及キーワードの抽出」機能です。
これは、競合はAIに取り上げられているのに、自社は取り上げられていないクエリを自動で一覧表示してくれるものです。
この機能を使えば、自社が今後対策すべきキーワードが明確になり、AIに露出するためのコンテンツ制作方針が立てやすくなります。
3. 実際の活用事例:金融業界におけるLLMO最適化のケーススタディ
たとえば、「18歳 クレジットカード」という検索クエリにおいて、ある競合企業が「高校生はクレジットカードを作れない」という短く明確な文章を記事中に含めていたため、Google AI Overviewにそのまま抜粋・表示されました。
一方、別のブランドは「原則として18歳以上であれば申し込み可能ですが…」といったやや冗長な表現になっており、AIが回答として抜き取るには不向きと判断された結果、言及されませんでした。
このように、単に情報を記載するだけでなく、「AIが抜き取りやすい構造で記述すること」が重要になります。
これはいわゆる“LLMO的構造最適化”と呼ばれるもので、Brand Radarで発見したクエリに対して、構造化・簡潔化・見出しの整理といった改善を行うことで、AI露出の確率を大きく高めることができます。
4. LLMOにおけるコンテンツ制作の5つの鉄則
AIに取り上げられる確率を高めるためには、従来のSEOとは異なるアプローチが求められます。
以下は、Brand Radarで得られた示唆をもとに整理された「LLMO時代のコンテンツ制作の鉄則」です。
4.1 明確かつ簡潔な表現を心がける
AIは、読者に代わって要点を抽出する役割を果たすため、「明確な主語・述語構造」「簡潔な結論」が重要になります。
たとえば、ファクトを端的に述べた一文(例:「18歳以上であればクレジットカードの申込が可能です。」)はAIが好む記述です。
一方で、「〜とされています」「〜かもしれません」などの曖昧な表現は避けるべきです。
これは人間が読むには丁寧でも、AIにとっては不確実性を増すノイズと捉えられるからです。
4.2 質問形式の見出しを使用する
AIはしばしば、Q&A形式のページから直接回答を引用します。
したがって、「◯◯とは?」「◯◯の使い方とは?」といった質問形式の見出しを活用し、その下に簡潔な答えを配置することで、抜粋対象になりやすくなります。
この手法は、FAQページや辞書的な情報サイトではすでに実装が進んでいますが、一般的なブログや企業メディアにも応用が可能です。
4.3 権威性・信頼性の担保
AIは、信頼できるソースから情報を得ようとする傾向があります。
したがって、自社メディアにおいても、以下のような工夫を凝らすことが有効です。
-
執筆者の肩書や経歴を明示
-
根拠となる出典・統計データを明記
-
第三者機関や公的機関へのリンクを設置
これらの工夫により、AIがコンテンツを「信頼できる」と判断しやすくなります。
4.4 最新性を担保する
特にYMYL(Your Money, Your Life)領域では、情報の“鮮度”がAIにとって重要視されます。
医療、金融、法律、育児、教育といったジャンルでは、「最終更新日」「記事のアップデート履歴」などが明記されているかどうかも、AIの評価に影響します。
4.5 構造化データと視覚的補足の活用
AIはHTML上の構造など構造化データも読み取って内容を判断します。
FAQ、HowTo、Productなどを適切に使用することで、AIが正確に情報を抜粋しやすくなります。
また、表・図・リスト・箇条書きなどの視覚的整理も有効です。
特に「手順」「比較」「メリット・デメリット」などは、リスト形式で記述することでAIへの取り上げ率が上がります。
5. SEOとLLMOの関係性:共存か、代替か?
SEOとLLMOは、決して対立する概念ではありません。
むしろ、AIによる情報流通が加速する現代においては、両者を統合的に捉えたマーケティング戦略こそが求められています。
従来のSEOでは、「検索キーワードへの最適化」「タイトルや見出しへのキーワード挿入」「被リンクの獲得」などが中心でした。
これらはGoogleのクローラーに対する最適化であり、人間が検索結果を一覧で見てクリックすることを前提とした設計です。
一方、LLMOでは「検索結果を介さずに、AIが即座に回答する」という文脈の中で、AIに「取り上げられやすい文体・構造・表現」を模索することが重要です。
| 項目 | SEO | LLMO |
|---|---|---|
| 対象 | Googleなどの検索アルゴリズム | LLM(大規模言語モデル) |
| 最適化単位 | キーワード・リンク・タグ | 表現・構造・信頼性 |
| 成果の指標 | 検索順位・CTR・CV | 言及数・回答抜粋・AI回答率 |
結論として、SEOとLLMOは「車の両輪」のようなものであり、相互に補完し合う戦略が求められます。
たとえば、SEOで上位表示されていればAIに学習される確率も上がりますし、LLMO的な明確な文章構造はSEOにおいてもユーザー体験の向上に寄与します。
6. Google AI OverviewとLLMO:仕組みと対策のポイント
Google AI Overview(旧:Search Generative Experience)は、ユーザーがGoogle検索を行った際、検索意図を読み取り、関連情報を自然言語で要約・生成して表示する機能です。
この仕組みにおいて、AIがどのサイトから情報を取得しているのかはブラックボックスですが、実際に観察されたパターンから、以下のような傾向が読み取れます。
6.1 明確な一文が抜粋されやすい
AI Overviewは、段落中にある「端的な一文」を抜粋して引用する傾向があります。
特に、FAQ形式・辞書形式の文章が好まれます。
例:
-
「クレジットカードは18歳以上で申し込み可能です。」(←抜粋されやすい)
-
「原則として…また一部例外もあり…詳細は以下をご参照ください。」(←抜粋されにくい)
6.2 構造化とマークアップの活用
Googleは構造化データをもとにAIが判断する精度を高めています。
FAQ 、HowToなどの使用は、AI Overviewでの抜粋確率を高める施策としても有効です。
6.3 信頼性の評価
信頼性が不明なサイトはAI Overviewから除外される傾向があります。
医療や法律、金融などのYMYL領域では、特に執筆者情報や引用元の明記が重要です。
7. LLMO対策の社内導入ガイド:マーケ・編集・経営陣の役割
LLMO対策は、単なるWeb担当者やSEO担当者だけの業務範囲を超えます。
組織全体で意識と役割を共有することが不可欠です。
7.1 編集・ライティングチームの役割
-
明確な構文、簡潔な要約、Q&A形式の導入
-
誤解を生みにくい言い回しの徹底
-
リスト化、表形式などの視覚的補足の活用
7.2 マーケティング部門の役割
-
Brand Radarなどのツール活用によるギャップ分析
-
コンテンツの優先順位付けと更新サイクルの設計
-
競合との差分モニタリングとアラート体制の構築
7.3 経営陣の役割
-
LLMOを意識したブランド戦略の明確化
-
情報公開方針の整備(執筆者、企業理念、第三者評価など)
-
AI時代に適応したWebガバナンス体制の構築
8. 今後の展望と課題:AI進化とともに変わる最適化指標
AI技術の進化は今後さらに加速すると予想されており、それに伴い「AIに取り上げられる」ことの重要性も高まっていくでしょう。
しかし、LLMOにもいくつかの課題が残されています。
8.1 AIの出典非開示問題
AIは情報の出典を明記しない場合が多く、ブランド露出が「認知」に留まり、クリックやCVに直結しないリスクもあります。
今後は「言及→想起→行動」という流れを設計する戦略が不可欠になります。
8.2 ファクトチェックの重要性
AIは誤情報を生成するリスクもあります。
したがって、自社が提供する情報が正しくAIに理解されるよう、「正確なファクト」と「誤解のない記述」を徹底する必要があります。
8.3 LLMO評価指標の標準化
現在はBrand Radarのようなツールが一部提供されていますが、業界全体でLLMOの「効果測定指標」や「業界ベンチマーク」が整備されていないため、標準化が今後の課題となります。
結論:LLMOは未来のSEOである
今やSEOは、「検索エンジン最適化」から「生成AI最適化」へと変革しつつあります。
Brand Radarのようなツールを活用することで、AI時代の新しいマーケティング指標を数値化し、現実的な改善施策へと結びつけることが可能です。
LLMOは単なるトレンドではなく、企業のコンテンツ戦略における中核的要素となっていくでしょう。
今後ますます増えるであろうAI起点の情報接触に備え、今こそ企業は「AIに好かれるコンテンツとは何か」を本質から問い直し、継続的な対策と改善を進めていくことが求められています。
ご紹介したahrefsはこちら:https://ahrefs.com/ja
※この記事では、特定のウェブサイトを取り上げていますが、これはあくまで解説のためでありLLMO対策における具体的な一例です。
本記事は広告ではなくあくまで使用例でありサイト自体を評価する意図もございません。
この記事を書いた人