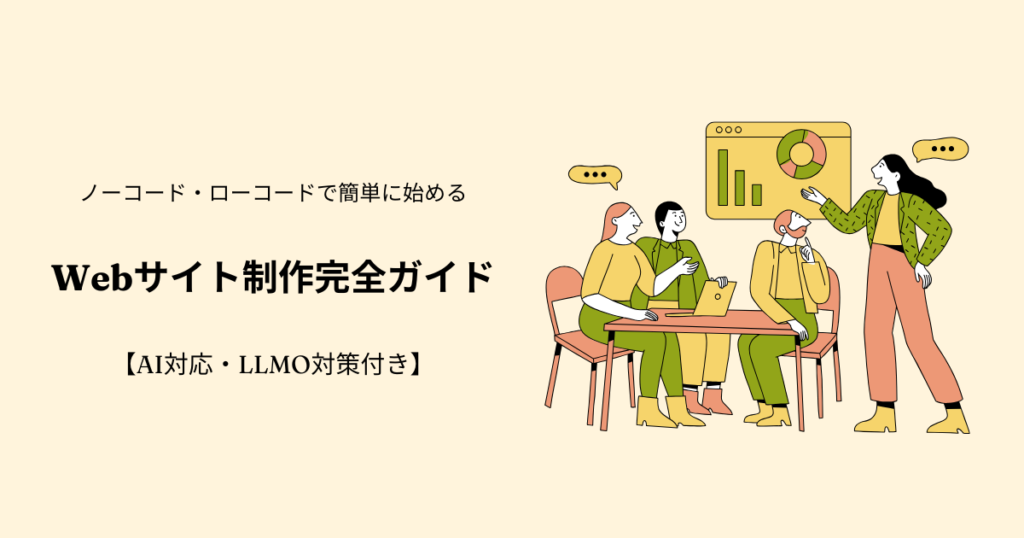 Web制作は、もはやコードを書かなくてもプロ品質のサイトを構築できる時代になりました。
Web制作は、もはやコードを書かなくてもプロ品質のサイトを構築できる時代になりました。
ノーコード・ローコードの活用により、デザインや更新のスピードを格段に向上させつつ、コストを抑えられます。
本記事では、主要ツールの比較に加え、AI支援機能の最新動向、料金体系まとめ、そして近年注目の「LLMO対策(大規模言語モデル最適化)」についても解説し、検索エンジンや生成AIとの相性にも配慮したSEOに強い記事構成を提供します。
目次
ノーコード・ローコードとは何か
定義と違い
ノーコードはプログラミングを書かずに視覚的なエディタやテンプレートでWebサイトやアプリを作成する手法です。
ローコードは最小限のコードやスクリプトを組み合わせてカスタマイズ性を高める手法を指します。
どちらも目的は開発効率の向上と内製化の促進です。
なぜ今注目されるのか
人手不足や開発コストの高騰、ビジネス側のスピード要求により、外注せず社内で迅速にサイトを立ち上げ・改善するニーズが高まっています。
AIの導入でコンテンツ生成やデザイン提案の自動化が進み、より短期間で価値の高いサイトを作れるようになってきました。
ツール選定の基本観点
目的別チェックリスト
選定時には次の観点で評価します、目的と期待する成果に合わせて重みづけしてください。
-
用途:ランディングページ、コーポレート、EC、ブログなど用途別に最適なツールが変わること。
-
デザイン自由度:ビジュアル重視かテンプレート重視かで選択肢が変わること。
- AI支援機能の有無(自動生成、文章・画像・構成補助など)
-
CMS・更新頻度:記事や商品を頻繁に更新する必要があるかどうか。
-
スケール性:将来的にページ数やアクセスが増えた時の対応力。
-
エクスポート/移行性:将来的にコードやデータを別環境に移したいか。
-
SEO機能:メタ設定、構造化データ、サイトマップ生成などの可否。
-
外部連携:決済、フォーム、メール配信、外部データベースとの連携の有無。
-
費用対効果:初期コストとランニングコストのバランス。
- LLMO対策対応(生成AIに有利な構造を配慮できるか)
料金と拡張性の見方
料金は無料プランの有無、独自ドメイン対応、帯域やページ数上限、CMSアイテムの上限などで差が出ます。
ツールによってはCMSやEコマース機能が別プランで提供されるため、将来の拡張を想定してプランを選んでください。
具体的な料金例としては、WebflowのサイトプランはBasicやCMS、Businessなど複数層があり、用途に応じて月額が変わる点に注意が必要です。
主要ノーコード・ローコードサイト制作ツール比較
比較表(h3)
以下は2025年時点で広く使われている主要ツールの簡易比較表です。プランや機能は変わるため、導入前に公式ページで最新情報を確認してください。
| ツール | 無料プラン | 有料プラン(月額換算) | AI支援 | エクスポート | 得意な用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| STUDIO | あり | 980円〜/月(国内プラン) | 自動レイアウト | × | コーポレート、ポートフォリオ |
| Webflow | なし/トライアル | Basic $18/CMS $29/Business $49以上 | デザイン補助 | ○ | デザイン重視、中〜大規模サイト |
| Wix | あり | 500円〜2,500円程度 | AIサイトビルダー | × | 多目的、小〜中規模サイト |
| Jimdo | あり | 900円〜1,900円程度 | AI生成(Dolphin) | × | 小規模・初心者向け |
| Elementor (WP) | あり | Pro ¥5,000/年〜(サーバ別) | AI文案支援 | WP依存 | WordPressサイトの自由編集 |
| ペライチ | あり | 1,000円〜/月(プレミアム) | 自動ブロック配置 | × | LP、キャンペーンページ |
※料金は2025年8月時点の公式情報または一般公開情報をもとに目安として記載しています。変動するため導入前に公式サイトで最新情報をご確認ください。
各ツールの長所と短所を掘る
STUDIO
長所
-
直感的な操作性:デザインソフトのような感覚でレイアウト編集が可能。PhotoshopやFigma経験者なら即戦力で扱える。
-
日本語UIと国内サポート:国産ツールなので、言語の壁や海外サポートの遅延がない。
-
CMS機能搭載:ブログやお知らせページなど、更新が頻繁なコンテンツも内製化可能。
-
無料プランでも基本機能が使える:初期コストを抑えながら本格的なサイトを構築可能。
-
レスポンシブ自動対応:スマホ・タブレット・PC表示が自動で最適化される。
短所
-
多機能ゆえ学習コストあり:初めて使う人にとっては機能が多く、全貌を把握するまで時間がかかる。
-
拡張機能は限定的:海外ツールに比べて外部サービス連携やプラグインの種類が少ない。
-
完全なオフライン編集が不可:常にインターネット接続が必要。
Webflow
長所
-
高度なデザイン自由度:HTML/CSS/JavaScriptの制限をほぼ受けず、完全カスタムが可能。
-
コードの書き出しが可能:制作後のソースコードをダウンロードでき、他サーバーでも運用可能。
-
CMSとアニメーション機能が強力:高度な動きやデータベース連動型サイトが実現可能。
-
海外での利用実績豊富:世界中のデザイナー・企業に採用され、情報量が多い。
短所
-
英語UI:日本語未対応のため、英語が苦手な人にはややハードルが高い。
-
学習曲線が急:本格的な機能を使いこなすにはCSSやWeb構造の理解が必要。
-
価格はやや高め:高度な機能やホスティング込みプランは月額が高額になりやすい。
Wix
長所
-
テンプレートが900種類以上:業種や目的に合ったデザインをすぐに利用可能。
-
ドラッグ&ドロップで簡単編集:初心者でも数時間で形になる。
-
アプリマーケットの充実:SEOツール、予約システム、チャット機能などを簡単に追加できる。
-
AIサイトビルダー搭載:質問に答えるだけでデザインと構成を提案してくれる。
-
無料プランあり:広告表示やドメイン制限はあるが、試しに使うには十分。
短所
-
テンプレート切り替え不可:サイト制作途中で別デザインに変更できない。
-
読み込み速度が遅くなる場合あり:多機能ゆえ、画像やスクリプトが増えると表示速度が低下しやすい。
-
独自ドメイン利用は有料プラン必須:ビジネス用途なら必然的に有料契約になる。
wix.com
Jimdo
長所
-
AI自動生成(Dolphin):質問に答えるだけで、文章・画像・レイアウトを自動生成。
-
自由編集モード(Creator):より細かくデザインを調整できる。
-
シンプルな料金体系:機能ごとに複雑なオプションがなく分かりやすい。
-
サーバー不要:Jimdoの環境に全てホスティングされるため管理が楽。
短所
-
デザイン自由度は低め:特にDolphinモードでは細部のカスタマイズが制限される。
-
外部連携機能が少ない:他サービスとのAPI接続などはほぼ不可。
-
複雑な機能は非対応:大規模なECや会員制サイトには不向き。
jimdo
Elementor(WordPress)
長所
-
WordPress対応:既存のWPサイトにも後付け可能。
-
高度なデザイン自由度:テーマ編集やウィジェットの追加が容易。
-
AIアシスト機能搭載:テキストや画像生成、レイアウト提案を自動化。
-
豊富なテンプレートとアドオン:公式・非公式の素材が膨大。
-
WooCommerce完全対応:ECサイト構築にも向く。
短所
-
WordPress環境必須:サーバーやセキュリティ設定は自前で行う必要がある。
-
プラグイン依存度が高い:過剰にアドオンを使うと表示速度が低下する。
-
学習コストあり:WPとElementor両方の操作を理解する必要がある。
Elementor
ペライチ
長所
-
超シンプルな操作性:必要なブロックを選んで配置するだけ。
-
ランディングページ特化:1ページ完結型のサイトを短時間で作れる。
-
日本語UIと国内サポート:説明やヘルプも分かりやすい。
-
SEOやSNS連携も可能:シンプルながら集客施策も対応。
-
無料プランあり:小規模キャンペーンやテスト運用に最適。
短所
-
複数ページ構成には不向き:中〜大規模サイトの構築は難しい。
-
デザインの自由度が低め:テンプレートの制限が多く、細かい調整は難しい。
-
高度な機能は有料:決済機能やフォーム拡張などは有料プラン限定。
ペライチ
実践ステップ:0から公開まで
1 企画と要件定義
手を動かす前に次を明確にします。
-
目的(問い合わせ獲得、商品販売、ブランド訴求、情報提供)
-
KPI(CV数、問い合わせ率、滞在時間)
-
ページ構成(トップ、サービス、事例、料金、ブログ、問合せ)
-
更新頻度と担当者(誰がいつ更新するか)
-
必要な連携(決済、会員、メール配信、CRM)
これにより最適なツールとプランが定まります。
2 ワイヤーフレームとコンテンツ設計
ページごとに目的を一文で定義し、導線を作ります。
トップページは最重要指標を最初に提示し、CTAを明確にします。
画像やテキストの原稿、必要な資産(ロゴ、写真、動画)を事前に準備してください。
3 デザインと組み立て
テンプレートをベースに作る場合でも以下の点を意識します。
-
レスポンシブ確認は必須です。モバイルを第一にチェックしてください。
-
画像は適正な圧縮でアップロードし、遅延読み込みを利用します。
-
フォントや色はブランドガイドラインに沿って統一します。
-
フォームは必須項目を最小化し、プライバシー表記を明示します。
4 公開前の最終チェックリスト
公開前に必ず確認する項目を列挙します。
-
独自ドメイン設定とSSLの有効化
-
Meta title, descriptionの最適化と重複確認
-
canonical設定と重複コンテンツ対策
-
サイトマップXMLの生成と送信準備
-
モバイル・PCでのレイアウト確認と速度測定
-
フォーム送信確認とメール通知動作確認
-
アナリティクス(GA4)とSearch Consoleのタグ設置
5 公開後の運用と改善
公開後はデータを見てPDCAを回します。
最低でも最初の3か月はアクセス解析、コンバージョン率、離脱率を見て改善を続けます。
A/BテストやCTAの改善を行い、コンテンツ追加の計画を立てます。
SEO対策と技術的注意点
基本対策
ノーコードで作る場合でもSEOの基本は変わりません。
重要なのはコンテンツの質と技術的な実装の両輪です。以下は必須チェック項目です。
-
各ページのtitleとmeta descriptionを最適化すること。
-
見出し(h1, h2, h3)の論理的な階層を保つこと。
-
画像にalt属性を入れ、ファイル名も意味のあるものにすること。
-
内部リンクを適切に張り、パンくずリストを導入すること。
構造化データとサイトマップ
リッチリザルトを狙うためにschema.orgによる構造化データを導入します。
商品、記事、組織、パンくずなどを検討してください。
サイトマップXMLは自動生成できるツールが多く、Search Consoleへ登録しましょう。
ツールによっては自動でサイトマップを生成する機能がありますので活用してください。
Google Search Console
サイト速度とモバイル最適化
モバイルファーストの時代においてページ速度はランキング要因かつユーザー体験に直結します。
画像最適化、不要なスクリプト削減、遅延読み込み、CDN利用などを実施してください。
WixやSTUDIOなどのホスティング型サービスは最適化機能を提供していますが、プラグインの入れすぎや外部スクリプトは速度悪化の原因となりますのでご注意ください。
CMS運用とSEO
大量の記事や商品を扱う場合はCMSのスキーマやURL規則、カテゴリ構造を最初に設計しておくとSEO上有利です。
よくある失敗と対策
① テンプレ頼みでコンテンツが薄くなる
テンプレートは見た目を整える一方で、コンテンツの差別化が必要です。
事業の強みや実績、顧客の声を盛り込んでコンテンツを厚くしたり、素材は有料のものや実際の写真を使用すると良いでしょう。
② フォームや計測の未整備
問い合わせフォームやコンバージョン計測が整っていないと効果測定ができません。
公開前に必ず通知やタグの動作をテストしてください。
③ 将来の移行を考えていない
初期はホスティング運用で十分でも、将来に渡り自社で完全に運用したくなる局面が来ます。
コード出力やデータエクスポートの可否を確認しておきましょう。
④AI文章そのまま使って識別される
AIで出力した文章の校正を行ったり、独自語り、経験談、実際のお客様の声などを盛り込むことでカバーが可能です。
業種別おすすめ構成例
小規模店舗・サービス業
構成例 トップ、メニュー・料金、予約・問い合わせ、アクセス、顧客の声、ブログ(お知らせ)。ランディング重視で電話や予約への導線を最短にします。
ペライチやWixが向いています。
コーポレートサイト
構成例 トップ、事業紹介、導入事例、採用、IR、問い合わせ。
ブランド訴求と採用訴求が重要ならSTUDIOやWebflowでデザインとCMSを整備すると効果的です。
ECサイト(h3)
構成例 トップ、カテゴリ、商品詳細、カート、マイページ、決済、配送・規約。
EC機能はプラットフォームの対応可否が重要です。
ShopifyやWixのEコマース機能などを検討してください。
コンテンツサイト・メディア
構成例 トップ、カテゴリ別一覧、記事詳細、タグ、検索、著者ページ。
大量記事を運用するならCMSの拡張性や検索機能、編集者管理が重要です。
WebflowのCMSやWordPress + Elementorなどの組合せが有力です。
将来を見据えた移行と拡張性
エクスポート・移行戦略
将来エンジニアに引き継ぐ可能性がある場合、コード出力やデータエクスポート機能があるツールを選ぶと移行コストが下がります。
Webflowはコード出力が可能で、静的なHTML/CSS/JSを取得して別環境で運用する選択肢があります。
API連携と外部DB
会員管理や業務データと連携する場合、AirtableやZapier、Makeなどを介した接続が便利です。
ノーコードツールと外部サービスの組合せで複雑な業務フローを構築できます。
将来的に独自機能が必要であれば、最初からAPI対応やWebhookが使えるツールを選んでください。
最新のAI対応ノーコードツール動向
-
WixのAIサイトビルダー:質問形式で構成とデザインを自動決定し、文面も提案される機能。
-
WebflowのAIによるデザイン補助:テンプレート提案やクラス設計等をAIで支援。
-
ElementorのAI文案生成:見出し・本文・キャッチコピーを自動生成するアドオン。画像生成も標準装備されつつある。
-
Jimdo Dolphin:選ぶだけでページ構成と文章を自動生成する日本語AI対応。
-
STUDIO:正式なAI生成ではないが自動レイアウト機能で配置を支援。
これらのAI対応機能は、制作スピードを大きく向上させる一方で、LLMO(Large Language Model Optimization)への配慮も必要です。
AI生成文だけでは検索エンジンや生成AIが識別可能なパターンとなり、オリジナリティや評価に影響する可能性があります。
実践ステップ:企画〜公開まで【AI活用編】
-
企画段階:何をAIに任せるか、どこを独自の解説にするかを決める。
-
ワイヤーフレーム:AI生成案をテンプレートとし、それに独自視点や事例を上乗せする。
-
デザイン・構成:AI支援機能を使い構成案を作り、その後人間の目で磨きをかける。
-
公開前チェック:AI生成文と独自部分のバランスチェック、LLMO対策を最終確認。
-
運用と改善:GA・Search Console・生成AIの応答を確認し、AIが生成するコンテンツで差別化ポイントを補強。
LLMO対策:生成AIが読んで評価する記事とは
「LLMO対策」は、AI時代のコンテンツ品質最適化手法です。
生成AIが記事をどのように解析して評価するかを意識した設計・執筆のことを指します。
以下の対策を実施することで、検索エンジンと生成AI両方に評価される記事になります。
LLMO対策ポイント
-
独自視点・具体例の挿入:事例、ユーザー体験、差別化された見解を盛り込み、AIが「模倣文」と識別しにくくする。
-
構造化された見出しと段落:h2、h3を論理的な階層にし、見出しを明確に。「読ませたい見出し」を意識。
-
定性・定量データの併用:導入効果、速度比較、料金表など数字で裏付ける。
-
語彙の多様性:「ですます」調を活かしつつ同義語や表現の変化でAIの平坦判断を回避。
-
質問形式や想定読者への語りかけ:読者の疑問に応答する形式で構成することで、人間らしさを担保。
-
結論を明確にする:結論が曖昧だとAI評価が下がる傾向、各セクションに明確な結論を設ける。
-
メタ情報やschema記述:HTML構造にschema.orgタグを入れて供給構造を示すことでAIと検索の双方に優位。
LLMO対策をもっと詳しく知りたい方はこちら
実務で使えるチェックリスト
導入前チェック
-
目的とKPIが定義済みか
-
更新担当者と頻度が決まっているか
-
必要な外部連携が洗い出されているか
-
予算と運用コストが確認済みか
公開前チェック
-
ドメインとSSLが設定済みか
-
メタ情報とOGPが設定済みか
-
構造化データとサイトマップが用意されているか
-
速度とモバイル表示を確認済みか
運用チェック(月次)
-
GA4とSearch Consoleの指標確認
-
コンバージョン率、流入経路の変化を確認
-
コンテンツの更新計画の進捗確認
ノーコード・ローコード導入の費用感とROI
初期費用を抑えて短期間で効果を出すのがノーコード導入の魅力です。
小規模サイトであれば無料プランや月額1,000円台から始められるケースが多く、CMSやEコマース、独自ドメインなどの要件が増えると月額が上がります。
投資対効果を上げるポイントは、初期段階で「最低限の機能」でテスト運用し、データを基に改善サイクルを回すことです。
ツールごとの料金やプランは頻繁に変化しますので、比較時は公式の最新情報を確認してください。
まとめとおすすめの組み合わせ
ノーコード・ローコードでのサイト制作は、目的に応じて最適なツールを選べば短期間で高い効果が得られます。具体的なおすすめ例は以下です。
-
短期LPやキャンペーンなら ペライチ + Wix AI文案
-
デザイン自由度と移行を重視するなら Webflow + AIデザイン補助
-
国内対応で更新運用まで重視するなら STUDIO(日本語CMS)
-
WordPressを既に使っているなら Elementor Pro + AI文案生成
最終的には「目的」「運用体制」「予算」「将来の拡張性」を軸に選ぶことが失敗しないコツです。まずは無料プランで試し、数週間の実運用で問題点を洗い出してから有料プランへ移行することを推奨します。市場の最新動向やツールの機能は頻繁に更新されますので、導入前には公式情報や比較記事を確認してください。
ちなみに弊社ではノーコードツールは使用せずオリジナルデザインのサイト制作を行っております。
ご興味ありましたら下記もご覧ください。
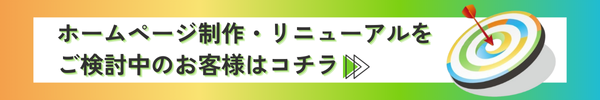
この記事を書いた人



